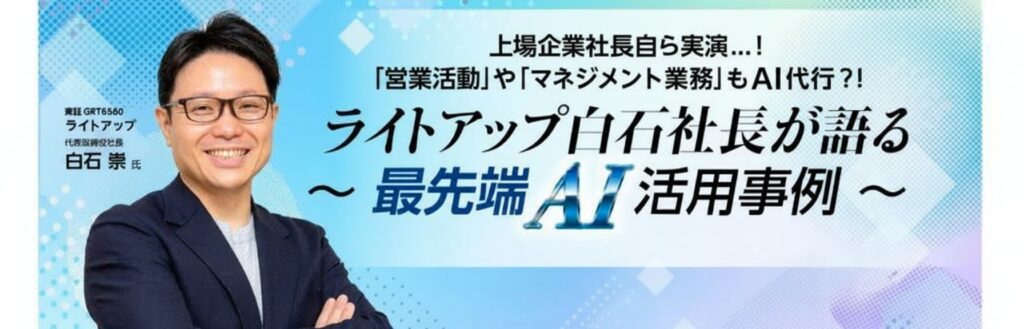【vol.3】AIが3人分の編集部になる──品質も自動で守る仕組み
【登場人物紹介】
西村果林:ライトアップ AI企画部リーダー。品質と運用の両立に関心を持つ。
白石 崇(Taka):ライトアップ代表。AIを“人間の編集部”のように働かせる仕組みを設計。
西村:前回は、AIの「稼働は無限大」というお話を伺いました。
今回はその続きとして、“量を増やしても品質を落とさない仕組み”──つまり、AIがどのように人の編集部のように動いているのかを聞いていきます。
ChatGPTとの違いは「完全自動化」
西村:最近はChatGPTを使って自分で記事を作る企業も多いですが、ハチドリOMとはどう違うんですか?
白石:一番の違いは、完全自動化されていることです。
会議のログがGoogleドライブに保存されると、AIが自動で内容を判別してフォルダ分けし、そこから記事を作成。
さらに別のAIが校正とコンプライアンスチェックを行い、自動でアップまでしてくれます。
西村:まさに編集部ですね。
白石:はい。ライター・校正者・コンプライアンス担当──3人分のAIが役割分担して動いているんです。
「AIが言ってないことを書くのでは?」という不安
西村:AIが“言っていないこと”を勝手に書いてしまう心配はありませんか?
白石:そこはきちんと三重チェックを入れています。
まず、日本語の自然さを確認するAI。
次に、個人情報や不適切表現を検出するAI。
最後に、インタビューログと照合して事実関係を確認するAI。
西村:なるほど、3段階なんですね。
白石:ええ。必要があれば人が最終確認することもできますし、出力された記事はスプレッドシートやメール通知で一覧管理も可能です。
「社員インタビュー」も“ゆるく”始めてOK
西村:社員インタビューを始めるときって、どう進めるのがいいんでしょう?
白石:あまり構えなくて大丈夫です。
たとえば会議ログや日常の雑談からでも記事化できます。
採用記事にしたい場合は、1人の社員に10本、20本分のテーマをまとめて話してもらうのもいい。
「今週の出来事を話す」ぐらいの軽い内容でも、立派なコンテンツになります。続けやすさが一番大事です。
まとめ
白石:AIを“人の編集部”のように動かす──それがハチドリOMの基本思想です。
量・質・安全性のすべてを保ちながら、企業の発信を止めない。
これからはAIと人が協働する“編集の共創時代”になると思います。
🕊 発信は「才能」ではなく「仕組み」で続ける時代。
AIが会話を記事に、記事を成果に変える。
ハチドリOMは、あなたの会社の物語を“止めない”ためのAI編集部です。
📩 気になる方は、ぜひ無料相談フォームへ。
「うちの会社でも導入できる?」「記事の自動化を試してみたい」など、まずはお気軽にご相談ください。