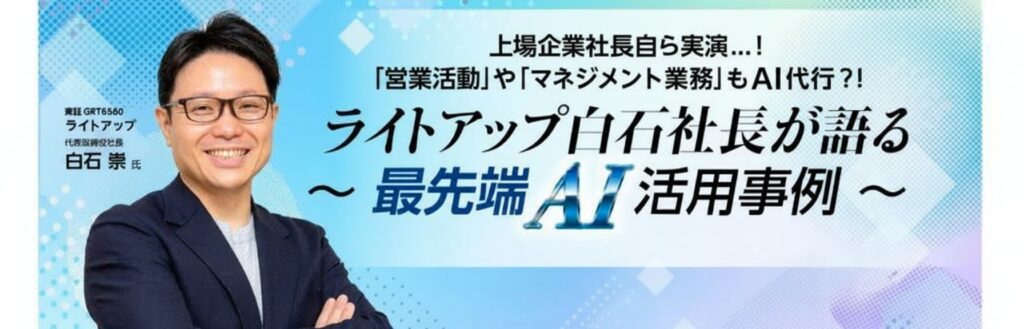【第3回】「刺さる営業メールの設計図」——“あるある→約束→具体→数字→一歩”の5段構成
【登場人物紹介】
川上:大手企業の営業マネージャー。BtoB商談で数百社を担当。メール文面の改善だけで返信率を倍増させた経験を持つ。
菅野:スタートアップ出身の営業マネージャー。SNS採用や法人営業を中心に、行動心理を踏まえた営業メッセージ設計を得意とする。
■ 導入文
「読まれない営業メール」から「反応が返る営業メール」へ——。
その境界を分けるのは、“感覚”ではなく構成設計だ。
第3回では、川上×菅野の二人が、現場で実証してきた「読まれる→動かれる」メールの型を具体的に語る。
共感で始める:“あるある”が一行目の最強フック
菅野: やっぱり最初の一文がすべてですね。
川上: うん。人って、最初の3秒で読むか決める。
菅野: よくある悪例が「このたび弊社では〜」。それ、誰も読まない(笑)。
川上: 一方で、「研修動画、見たら終わりになりがちですよね」って始まったら、読まざるを得ない。
菅野: そう。“あるある”で共感を取ると、相手の脳が「自分ごと化」するんですよ。
川上: 「あるある」で始めるって、“営業版のドアノック”なんですよね。
「約束」で次の行動を想像させる
菅野: 共感で開いたドアに、次は「約束」を入れる。
川上: 例えば「行動が変わる研修映像を設計しています」とかね。
菅野: うん。「単なる映像制作」じゃなく「行動が変わる設計」。この“約束”が大事。
川上: 約束=ベネフィットの提示。つまり「あなたの課題がどう変わるか」。
菅野: ここで“商品”を売るんじゃなく、“結果”を描くのがコツ。
「具体例」で信頼を積む
川上: 次に入れるのが、“実例”。
菅野: ですよね。「御社の安全研修を、受講翌週の点検行動をKPIに構成します」みたいな。
川上: 抽象で終わらせない。「誰の」「どんな状況で」使われたかを書く。
菅野: “行動が目に浮かぶ”文章は、信用になるんですよ。
川上: メールの信頼は、肩書きじゃなく“描写力”で生まれる。
「数字」で“信頼→納得”を完成させる
菅野: そして、数字。ここで一気に説得力が出る。
川上: 例えば「◯◯社で点検実施率+28%」。数字があるだけで“事実感”が跳ね上がる。
菅野: 逆に数字がないと、「ふんわり良さそう」で終わるんですよね。
川上: “結果を数値化できるかどうか”が、プロの境界線。
菅野: たとえ目安でも、「3倍」「半分」みたいな比較表現を使うと効果的です。
「一歩」で行動を促す
川上: 最後は、“行動のハードル”を下げる。
菅野: そう。「まず30分だけ擦り合わせませんか?」とか、「事例資料をお送りしますか?」。
川上: “とりあえず話そう”じゃなく、“軽く確認”レベルに落とす。
菅野: 「検討ではなく体験」に誘うのがポイントです。
川上: 人は“決断”より“確認”の方が心理的負担が小さい。だから、反応しやすいんです。
5段構成まとめ:「あるある→約束→具体→数字→一歩」
菅野: この5つ、どれも抜けたら弱くなる。
川上: そう。特に“あるある”と“具体”が抜けると、心が動かない。
菅野: 僕のチームでも、この5段構成をテンプレにしてます。
川上: 型があると再現性が出る。属人的じゃなく、チームで成果を上げられる。
菅野: “感覚営業”を卒業する第一歩ですよね。
まとめ:営業メールは“感情設計”のプロセス
川上: 結局、営業メールって“感情設計”なんですよ。
菅野: うん。文章じゃなく、**「読み手の感情曲線」**をデザインしてる。
川上: 「共感→期待→信頼→納得→行動」。
菅野: これを順番に並べただけなんですよね。
川上: そう思うと、メール1通も“設計物”。
菅野: まさに。「刺さる営業メール」は、設計で作れる。センスじゃない。
👉 次回予告:
最終回・第4回では、実際に既存の営業メールを**「刺さる型」にリライトする方法**を解説。
川上×菅野がリアルに“添削”しながら、明日から使える改善ポイントを伝えます。